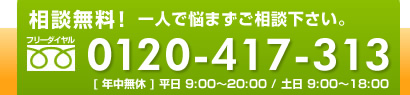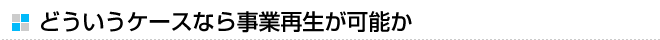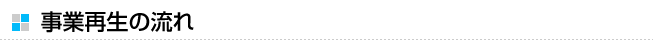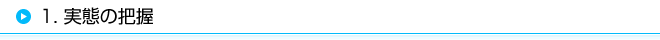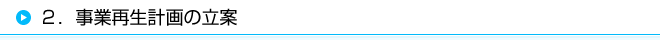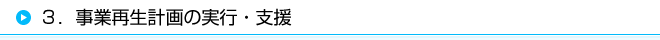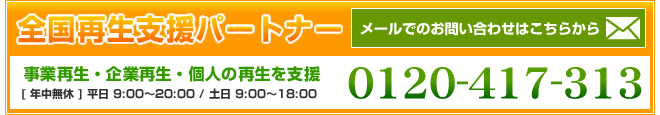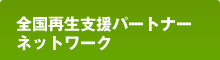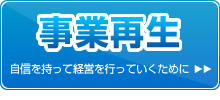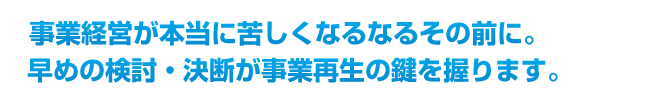
企業の経営が苦しくなったとき、倒産の危機に陥ったときに、そのまま資産を売却・破棄してしまうと事業価値が下ってしまい、再起は難しくなります。
事業再生とは、収益力・競争力のある事業を残し、採算のとれない事業を縮小・スリム化することで、
企業全体の再生をはかることを言います。その際、一時的な支払停止や支払期限の再スケジュール、
債務の一部免除や繰り延べなどを行うなど、再生のための様々な手立てを打ってゆくことが必要になります。
事業再生を行うための条件はズバリ2つ。
1. 負債がなくなる、または減額されれば、資金繰りが回復する
2. 再生すべき事業がある
上記2点の条件が成立するかどうかが、まず事業再生が可能かどうかの分岐点です。
一部または全部の負債がなくなったとしても、すぐに資金繰りが詰まってしまってしまうようであれば、
再生しても、すぐにまた同じ状況に陥ってしまします。
負債が減れば(なくなれば)資金繰りが回復する見込みがたっているというのが、まずは事業再生の第一条件となります。ついで、再生できる(利益がプラスになっている)事業が存在すること。再生すべき事業が
なければ、今後の見通しが立ちませんので、事業再生は難しくなります。
再生する事業を黒字化する、また黒字を維持する。また、資金力のある企業や個人にスポンサーとして
投資をしてもらう。大まかに言えば、こういった策を講じることで、事業を再生し、企業全体の再生を図っていく流れとなります。
事業再生は、事業実態を維持している間に行わないといけない、すなわち、企業の血液である資金が底をつく前に行わなくてはならず、スピードが要求されます。 限られた時間のなかで、何を行うのか、また何を捨て何を守るのかを判断し、そのための準備を行い、実行をすることになります。 事業再生の一般的な流れとしては、以下のようになります。
現状の決算書から実態を把握するため、本来の決算書を時価に戻す作業を行います。
時価に戻すために、現場や関係者とのヒアリング等を行っていきます。
この計算書を元に、財務・事業・業務(その他不動産など)に分けて分析・調査(デューデリジェンス)していきます。
分析結果から会社の問題点や、金融機関等の債権者に対しての弁済率等を算出します。
実態を把握した後、今の会社の実態数字や経営改善するための方法、またその方法を盛り込んだ事業再生計画を立案する。
このとき、どの事業再生の手法(会社分割や事業譲渡など)をとれば経営合理性が高いかの検討や、事業・財務・業務リストラ案の策定を行う。
また、税金の発生・法律問題も併せて最適な事業再生となるように検討します。
事業再生計画・事業再生手法の実行・サポートを行います。
また、2次破綻が起きないようにサポートを必要に応じて行います。