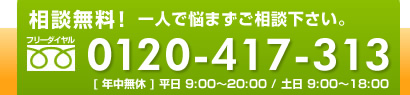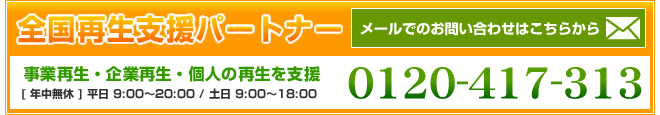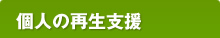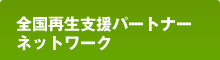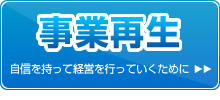必要な生活費を確保しながら原則3年で返済する個人再生(個人版民事再生)とは、裁判所に認められた再生計画に基づいて一定の借金を免除してもらう方法です。
一般民事再生手続きは、 法人でも個人でも行うことができますが、個人再生手続きは個人債務者の民事再生手続きに関する特則として制定されたものです。
個人といっても、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みが必要条件となります。
また債務額も住宅ローンを除いて5,000万円を超えないことが条件となります。 申し立ては債務者が行い、 債権者からは申し立てができません。
再生計画の法定議決も、一般再生手続きが債権者集会を開催するのが原則ですが、小規模個人再生においては書面による決議など要件が緩和されており、給与所得者等再生の場合は債権者の意見を聴取すればよく同意は必要ありません。
債務者は働きながら再生計画通りに返済し、 残りの債務の免除を受けることになります。返済期間は原則として3年間 (最長5年) の分割払いとなっています。

住宅ローンを抱え、なおかつ多重債務に陥った場合、自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を失うこととなります。 しかしながら、自宅を購入している人というのは、大抵自宅に対して非常に強い愛着を持っているものです。当然に自宅を手放したくないという希望があります。 この希望をかなえる手続きが個人再生なのです。
個人再生で、住宅資金特別条項の適用が可能な場合は、住宅ローンはそのままで、それ以外の一般債務を大幅に減額することがが可能です。 手続により決められた金額を原則3年間で分割返済( 特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。この借金には将来利息はつきません。)していくことで、住宅を手放すことなく経済的な再建をはかることができます
具体的には、住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能です。500万円を超え1,500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能です。1,500万円以上3,000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能です。3,000万円を超え5,000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能です
- ・住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円以下であることが要件となります(平成17年1月改正)。
- ・ 本人(債務者)自ら手続を行うことは大変難しく、ほぼ無理です。弁護士などの専門家に委任することになります。
- ・5〜7年間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりする事が出来なくなります。
- ・自己破産と同じく官報に掲載されます。(国が発行している新聞のようなものですが、通常一般の方はまず見ません。)
- ・個人再生手続きは半年〜1年の手続期間を要し、その後、原則3年間の返済期間があります。 減額されるとはいえ、最低でも100万円を再生計画に従って支払っていかなければなりません。 様々な外的要因によって収入が減額されたとしても、決められた計画通りに支払を続けなければならない訳です。 もし、支払が困難になった場合は再生を取り消されることもあり、破産を余儀なくされることもあります。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者再生の2種類の手続があります。 小規模個人再生手続は一般民事再生の特則であり、給与所得者再生手続は小規模個人再生手続の特則です。従って給与所得者再生手続は一般民事再生からすると二重の特則となっています。 給与所得者再生手続と小規模個人再生手続の違いは次の通りです。
利用資格条件として小規模個人再生は、将来、継続反復して収入を得る見込が必要であり、給与所得者再生は小規模個人再生を利用できる人のうち給与など定期的な収入の変動の幅が小さい(20%以内)と見込まれる者である必要があります。 また、小規模個人再生は、書面決議による反対債権者の2分の1以上または債権額の過半数の反対があると否決されます。給与所得者再生は決議は不要です。
申立人は、自分の住所を管轄する地方裁判所に個人再生の申し立てをします。
裁判所は申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定をします。
債務者は債権者一覧表を提出し、債権者は債権額に争いがある場合は異議を述べたり、評価の手続きをすることで、手続きの中で主張できる債権額を確定します。
債務者は所有する財産の目録を裁判所に提出します。
債務者は、支払方法を決めた再生計画案を作成します。
小規模個人再生手続きでは、債務者が作成した再生計画案に同意するかどうかの債権者による決議を書面で行います。
給与所得者等再生手続きでは、書面決議は行われず、債権者の意見を聴く手続きあります。
裁判所が認可の決定をして、それが確定することによって手続きが終了します。